中世の祈り 現代に再建
手がけた教会・修道院の建築は百件余
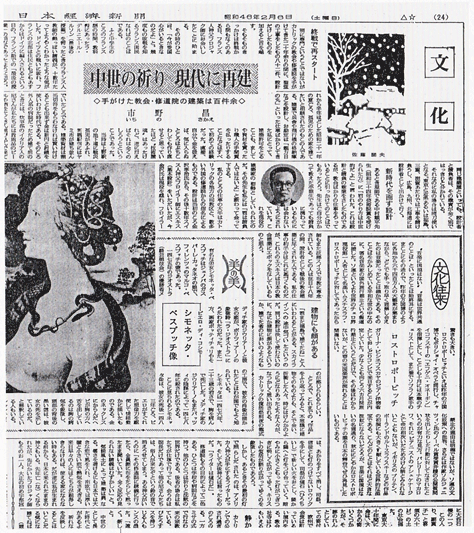
(昭和46年2月6日 日本経済新聞・文化欄に掲載されたものです。)
終戦で再スタート
別に専門ということではないが、カトリックの教会や修道院を手がけてきた20年余りの間に聖堂の工事をしたもの82件、設計だけしたものでも百を超す。
そもそものきっかけは終戦からまもなくのある日、フランス人神父フロジャック師にお会いしたことに始まる。そのときのひと言、「今が愛国心がいるときなのだよ」と。
幾度もの敗戦を知るフランス国民なればのことばである。
ふと中学生のころのフランス語の時間、教科書にあったラ・デルニエール・ルソン(最後の授業)を習ったときのフランス人教師の熱っぽい講義が、十数年たってようやくわかったような気がした。
ドイツとの戦いに敗れ、フランスの北部は住民ともどもあすからはドイツに編入されるという日のフランス語での「最後の授業」の描写であったように思う。私は陸軍での技術者暮らし十年に、終戦でピリオドを打ったのだがフロジャック師のことばが新しいスタートを決意させた。それから半年ほどした昭和21年の夏ごろ、孤児のための家を建てたいと相談されたのもこの人である。
陸軍で兵舎や飛行機の格納庫など設計し、お勘定は「親方日の丸」といった仕事ばかりしてきた私にとって、建築許可をとることもましてや資材を買ったり職人の手間賃を払ったりすることなどはすべて初めての経験だった。直接自分で金を扱えば、気に入らぬところはぶちこわしても作り直せると思っていたほど”技術屋魂”はあったけれど、逆に言えばそれは全くのしろうとということであった。
新世代を画す設計
あるとき恩師である中村順平先生(昭和34年芸術院賞を受けられた方)に「君のやり方は中世的だよ」と言われた。これは設計と請負の兼業をさしたものであるが、教会ばかりの仕事をやっていることにひっかけてのことばでもあったろう。先生はご自分がかつて教えた卒業生であっても請負に携わっているものには会わないようにされていた。これを現役の建築家の姿勢としていられたのだ。その先生も私には「君は請負人ではないよ」と断って会って下さる
私のところの仕事の大半はカトリックの各地方の司教区と、数多い外国の修道院からの指名によるものである。設計は当初のころ金沢孝治氏から、その後十数年スイス人神父フロイラー師にエスキス(基本設計)をいただいたが、今金沢氏は現役を離れ、フロイラー師もまた故郷スイスで布教に専念されている。この人は在日18年の間、設計者として戦後の教会建築に尽くされた人である。私の仕事の約半分はこれに基づくものだが、これらのエスキスは日本の教会建築のエポックをなしているものと思う。
建物にも顔がある
君また福島で建てたね。と人にいわれることがある。スカイラインへの途中気付いたというのだ。同じ設計は決して使わないのに、なにか建物に顔があるというか、建てた者のにおいのようなものが感じられるらしい。
ところで、これまでの”作品”をふり返ってみると、不思議に建物そのものよりも、そこで会い折衝した人々、時にはけんかのようにどなりあったような人々が、なつかしく思い出される。カトリックの復活祭前夜の儀式は、あかりをすべて消し、司祭、使徒とも灯のつけてないロウソクを手にして、司祭が燧石(ひうちいし)であたらしいをおこし、隣から隣へと灯をつけ合っていく。暗やみに小さくともった灯がつぎつぎに美しく広がってゆく。キリストの復活が語り広がってゆくのを象徴したものであろう。しかし、あるときその最初の灯で照らしだされたのは、アメリカ人神父が手にするライターだった。そして式後神父は言ったものだ。「ライターは燧石だ」。
修道院もその目的によって二色ある。ひとつは学校や病院などを持つ。他のひとつは祈りと沈黙の世界だけである。後者の場合は私たちが仕事で行っても、会うのは院長だけであって他の尼さんたちは、俗人が来たぞという鈴の音で消え失せてしまう。ある神父がいうのに「その修道院に講義に行ったら、全員顔に布をたらして黙ったまま聞いていた。全く反応の見られない講義は難しい」と。
気候風土によって建築は異なる。暑さを避けるにも日本では大きな窓で風を入れ、南欧では厚い壁と小さい窓で熱気をさえぎる。来日早々の人にはこちらが説得しきらなければ使える家にならない時もある。だが逆に私が生れる前から、日本に来られたままの神父もいる。先年亡くなられたが、先にかいたフロジャック師もそのお一人。大正初め宇都宮に大谷石で聖堂を建てたのもご自慢のお一つだった。この人、朝日賞を受けられたおり、副賞の50万円を「花より団子」と喜んだ事業家でもある。那須の60万坪(約198万平方メートル)の土地に精薄施設をもつなどの社会福祉法人 慈誠会を創設した。
東京大司教区の指名で、私が20年間に建てた10余りの教会の資金は大部分ドイツ・ケルン教区からの寄付ときく。先年ケルンでいくつかの教会に案内してもらったが、その時まだ第二次大戦被爆跡のれんが壁を残して小さな聖堂としているのも見た。手元をさいての寄付なのであった。欧州では都会でもいなかでも教会堂は町の中心に、前庭もなく建っている。日本の神社仏閣が美しい境内をもつのとは対照的である。教会は人々のつどうところ、社寺はひとりお参りするところともいえる。
静かに祈れる聖堂
カトリックもその元締めバチカンでの公会議の後、中世に形式化され過ぎた点を改めて新約聖書のころの純粋さに戻ろうとしている。一方ラテン語一点ばりだったミサの式などもその国のことばで行われるようになるなど、外来の宗教のにおいを取り去ってきている。だがゴシック式の高くのびたうす暗い中に、ステンドグラスを持つ聖堂に、教会らしさを感じる人もまだたくさんいる。フランスの農家のお年寄りが言っていた。「遠くても昔からの教会へ行く。新しい教会では祈れない」と。中世の聖堂がその信仰のあかしとして長い年月を費やし建てられた時代と現代とはあまりに隔たりがあるようだ。
祈れない聖堂は、祈れない現代を反映しているのだ、などと逃げることは、建築家としては出来ないことだ。静かにひとりお参りする気になれるような聖堂、それを建てねばならないと思っている。